大正初期、神谷末吉が碧南市松江町にて両口屋商店と称し、白しょうゆ・ソースの製造に着手。昭和13年、その商店を受け継いで日東醸造株式会社を立ち上げたのが日東初代の蜷川忠一だった。
昭和35年、忠一の息子蜷川義郎が2代目となった。義郎は電気技師になりたくて日本大学で勉学に励んでいたが、戦時中で夢は叶わず家業を継いだ。その頃は社員10名に満たない小さな工場で、麹づくりは三日三晩かかりっきりになるため昼も夜もなかったという。しかし、真面目にこつこつとやれば商売は上向いていき、貧しいながらも明るい時代だったという。
昭和50年代、後の3代目蜷川洋一は文系の大学で自由奔放な学生生活を送っていた。父から「跡を継いでくれ」とは一度もいわれなかったという。しかし就職活動で将来を真剣に考えたとき「しょうゆづくりをやりたい」と決心し、将来役に立つ仕事を父に紹介してもらい、酒・調味料の販売会社に就職。ホテルやレストラン、料亭などに商品を届けるルートセールスだった。自工場でつくったものがどのような流通でどのように使われているのかという勉強のためだということを洋一は後で気がついたという。父の工場に戻った洋一は、現場仕事を順番に覚えていき、次に営業をやった。
昭和60年代、2代目義郎は、今自分がつくっている白しょうゆに疑問を感じていた。原料である小麦や大豆は昔とは違い、アメリカから輸入したものだった。塩も三河湾沿いには海水からつくる本物の塩(饗庭塩)が豊富だったが、その頃の塩は工場生産したもので、にがりがない塩だった。
平成5年、2代目がこだわり抜いて取り組んできた「三河しろたまり」の販売がスタートした。味は本物だが値段は一般の白しょうゆの倍。息子の洋一は懸命に営業したが苦戦。しかし、自然食品が評価される時代へ少しずつ変わっていくにつれて、本物志向の料亭などで評価されるようになっていった。
平成6年に3代目となった洋一は、父の本物志向を受け継ぎ、おいしい水を求めて廃校となった山里の小学校を工場に改築して生産開始。奥三河の山深い里・足助の水とおいしい空気、厳選された素材を使って極上の味にたどり着いた。「足助仕込三河しろたまり」の販売がスタートしたのは平成11年だっ
た。
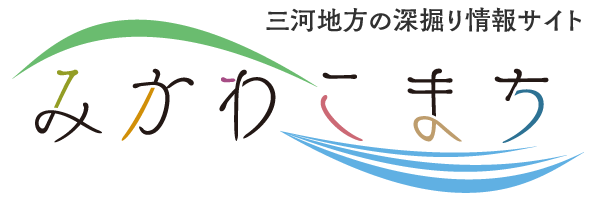



















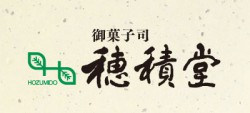









※この記事は2017年10月01日時点の情報を元にしています。現在とは内容が異なる場合がございます。