一人、黙々と赤馬を作る。「うまくできるかしら―」 不安を抱えながらも、指先を動かして形を整えていく。と、人の気配がする。「大丈夫、それでいいのだよ」そんな声が心に沁み込んでくる気がする。
「きっと祖母や母が、私に教えてくれているのだと思います」
伝統工芸品「吉良の赤馬」を受け継ぐ八代目、井上裕美さん(45歳)は静かに語る。母娘三代の絆によって、吉良の赤馬は今も継承されている。
郷土玩具として全国的に
吉良の赤馬は、吉良上野介義央公が赤馬に乗って領内を巡視したという、その姿を領内駮馬村の清兵衛が木彫りにして作り、子供たちに与えたのが始まりという。その後、木屑で作るようになり、天保年間に至り柳右衛門に相伝する。続く清助、伊太郎が世に広めた。田中清一(5代目)の時、郷土玩具として全国的にも注目されるようになった。
伝統を守るには大変な努力が
300年以上の伝統を継ぐ赤馬は、正麩(しょうふ)のりと木屑を練って、木型にはめ込んで作る。これを約二ヵ月間、日陰干しと日干しを繰り返し、最後に色を塗って完成させる。 伊太郎の時には、人形師、蒔絵師として西尾で工房を構えた。赤馬の他にも様々な人形を作っていた。長男の清一が継承する。 伊太郎の娘である、ゆきは東京に嫁ぐが、空襲で家を失う。そんな折り、兄の清一が病いで亡くなるという不幸が続く。清一は遺言で、妹のゆきに後を継いでほしいと言い残した。赤馬の木型は清一から、ゆきに渡された。 ゆきの一人娘、田中早夜子は岡崎市の百貨店に勤めるが、ゆきが高齢となったため、生地を練る仕事を手伝うことになる。やがて勤めをやめ、修業に専念する。 早夜子が、やっと仕上げた赤馬もゆきは全部壊してしまう。20年近く、早夜子の修業が続いた。母ゆきは88歳で亡くなった。 「きびしかったけど、技を伝えてくれた母には心から感謝しています。伝統を守るには大変な努力がいることを身をもって教えてもらった」と、早夜子は中日新聞の取材に応じ、話している。(2003年12月)「仕事を手伝ってくれている娘の裕美にも、母の教えを伝えていきたい」とも。 が、その早夜子は、娘に全てを伝えることなく、平成16年3月、66歳で他界した。
母の励ましの声が心に…
裕美さんは母の死の一カ月前に夫を亡くしていた。重なる不運に何も手につかなかった。赤馬のこともすっかり忘れていた。 一年も過ぎたある日、北海道から電話が入った。祖母や母の代からの赤馬の愛好家だった。母の死を告げると、「あなたの作ったものを買いたい。だから、やめないでほしい」と熱く語りかけてくれた。 裕美さんの心にぽっと灯りがついた。「私も赤馬を作っていこう」 とはいえ、色塗りの経験しかない。祖母や母の仕事ぶりを思い描きながら、生地を練り、木型にはめ、木型からぬくと指先で馬の形に整えていく。気の抜けない手作業。何度も失敗を繰り返す中で、母の励ましの声がそっと心に入り込んできた。
作っている人に会いたいから
「吉良の赤馬」は全国に根強い愛好家がいる。「作っている人に会って買いたいから」と、車や電車で西尾を訪れる。 三年前、裕美さんの娘、美春さん(当時中学3年生)が、産業振興協会主催の作文コンクールで、会長賞を受賞した。作文のタイトルは「吉良赤馬九代目として」。裕美さんは一度も継いでほしいと言っていないのに。 作文にはこう書かれていた。「母の姿を見ていて、私も作りたいと思った。いつか母を越えたい」と。
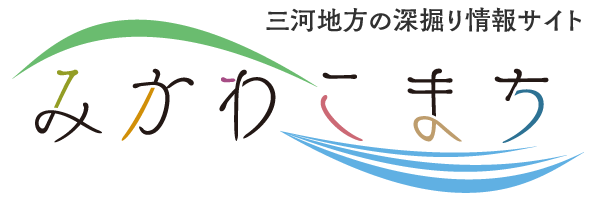














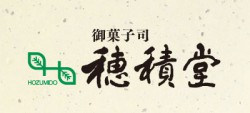












※この記事は2010年04月10日時点の情報を元にしています。現在とは内容が異なる場合がございます。