安城市東端町の西蓮寺に伝わる屏風で、現在は安城市歴史博物館に寄託されています。
「南蛮」は中国において南方に住む民族を指す蔑称で、平安時代には日本にも伝わり使われてきました。一六世紀なかば、ポルトガルやスペインをはじめとする国々から宣教師や商人が日本の南方からやってくると、彼らや彼らがもたらす貿易品を示す言葉として「南蛮」が定着しました。
そして、こうした外来文化に対する人々の関心は、洛中洛外図と並ぶ近世風俗画のテーマとして、百例近く知られる南蛮屏風を誕生させることになりました。
本作品の右隻には、日本の港において船から降りたカピタン・モール(ポルトガル全権大使)とその一行とそれを迎える日本の人々が描かれています。カピタンの一行には黒いローブをまとうイエズス会の宣教師がみえ、画面右上には屋根の上に十字架をかかげたキリスト教の教会もあります。左隻には異国の港町と出航する南蛮船が描かれています。
本作品は一六世紀末の神戸市立博物館所蔵の南蛮屏風(狩野内膳本)の系譜に位置づけられ、やや時期が下った寛永期(一六二四~一六四五)、一七世紀前半の制作とみられています。
個人的な注目点として、右隻中央には日本人とポルトガル人が抱擁する場面があります。本作品の絵師は、先行研究によって仏画風の体がぶよぶよした象を描くことから絵仏師的な知識を持つ町絵師が想定されていますが、今でも日本人には照れ臭いハグで挨拶を表現しているところをみると、どこから異国の情報を手に入れていたのか気になるところです。
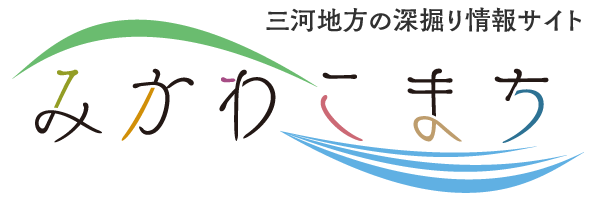

























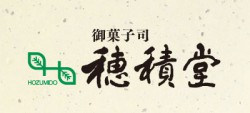

※この記事は2022年04月01日時点の情報を元にしています。現在とは内容が異なる場合がございます。