明治36年、初代喜三郎氏が、東海の瀬戸内海とも称される西尾市幡豆地区にて創業。今年で111周年を迎える尊皇蔵元。その歴史には様々な苦難があった。創業当時、他にない美味しい酒造りを始めるがなかなか思うようにはいかなかった。しかし愚直な努力は次第に実っていき、大正から昭和にかけては、一流といわれる「千石酒屋」の地位を築いていった。戦後の経営を委ねられた二代目一夫氏。自社ブランドであることに誇りを持ってやってきた三代目紳雄氏。
そして今から12年前、2003年の創業100周年を待たずして三代目紳雄氏が他界。36歳の若さで四代目蔵元となったのが現社長の厚夫氏である。厚夫氏が平成元年入社時に三代目の父から伝えられていたことがある。それは「本物の味を求め続ける」という、真面目に一生懸命取り組む酒造りへの姿勢だった。
四代目就任前、平成の始めの頃、酒業を取り巻く環境が大きく変わった。それまでは定価販売が基本で値引きは一切なかった。ところが、販売価格の自由化や酒販免許の緩和などによりスーパーやコンビニでもお酒が扱えるようになり、ディスカウント店が乱立し始めた。安売り競争は激化し、町の酒屋はすたれていった。全国の蔵元もその流れに巻き込まれていった。さらに、新潟から毎年招いていた技を持った蔵人が年々減少していった。先の見えない時期だったという。
そんな時期に就任した四代目は「このままではだめだ」と半年間悩んでいたという。そして新たなチャレンジに踏み切り、地元志向を強めていこうと舵を切った。北陸米を地元米に変え、作り方に関しても地元の蔵人を育てて、すべてにおいて「地元」にこだわる特長のある地酒造りが始まった。
それから数年で、純愛知産の新ブランドを次々に発売し、新しい販売経路も開拓していった。そして、創業当初からの主流ブランドである尊皇をさらに進化させていった。地味ながらも偽りなく、愚直に本物の味を求め続けてきた妥協なき職人魂が、尊皇蔵元復活の原動力となった。
老舗
三河地方にある老舗の創業から現在までを辿ります
SEARCH ENTRY
SOCIAL ACCOUNT
SPONSERED LINK
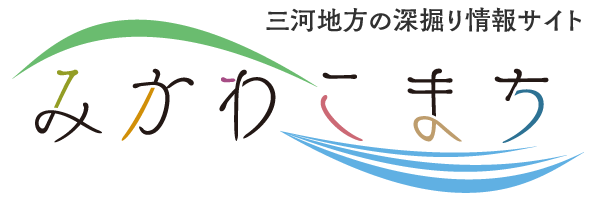






















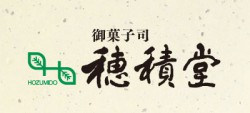




※この記事は2014年10月10日時点の情報を元にしています。現在とは内容が異なる場合がございます。